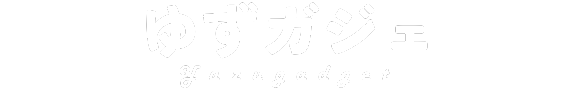コンパクトな筐体と高いコストパフォーマンスで注目を集めているミニPC。
近年では、GEEKOMやMINISFORUMなどからも高性能なモデルが続々登場しています。
そんなミニPCですが、「動画編集にも使えるの?」という疑問を持っている方も多いはずです。
動画編集はCPUやGPU、メモリ、ストレージなどの性能が求められるため、デスクトップPCやハイスペックノートが必要だと思われがちです。
この記事では、ミニPCで動画編集を行う際に必要なスペックや注意点、おすすめの構成をご紹介します。
そもそも…ミニPCで動画編集は可能か?

結論から言えば、ある程度の条件を満たせば可能です。
近年のCPUやGPUの高性能化と、省スペース型PCでもハイスペック構成が選べるようになったことが関係しています。
以前は内蔵GPUしか選べないモデルが多く、4K編集や複雑なエフェクト処理には不向きでした。
しかし、最近のミニPCは、Ryzen 9やCore i9クラスのCPUを搭載し、dGPU(ディスクリートGPU)に対応したモデルなども登場してきています。
ただし、注意したいのは「なんでも快適にこなせる」というわけではありません。
ミニPCはコンパクトさゆえに排熱性能や拡張性に制約があり、選ぶモデルや用途によって向き・不向きがはっきり分かれます。
 Yuzu
Yuzu拡張性を重視するならBTOや自作しかないです!




ミニPCで動画編集が向いているケース


- フルHD以下の解像度(1080p)でカット編集・テロップ・色調整などを行う場合
大体のYouTubeなどの動画サイトで主流なのはフルHD画質。ほとんどの方はこれくらいで十分です。 - 軽量な編集ソフト(例:Filmora、PowerDirectorなど)を使用
DaVinci ResolveやAdobePremiereProなどのソフトはある程度の高スペックが求められます。その分できることも多いのですが、色やエフェクト、機能面にこだわらなければ、ここまでのソフトは不要です。 - 長時間レンダリングをしない、または頻度が少ない
編集した動画は最終的に書き出し処理(レンダリング)が必要です。外部GPUがない場合、長尺の動画だと
向いていないケース


- 4K以上の高解像度編集が中心
- DaVinci ResolveなどGPU依存の高負荷ソフトを常用
- 長時間のバッチ処理や高度なエフェクト多用
動画編集に必要なミニPCのスペック要件


ミニPCで動画編集を行う場合、以下のスペックを基準に選びましょう。
CPU(プロセッサ)
最低:Intel Core i5(第10世代以上)/Ryzen 5 5000番台以上
理想:Intel Core i7・i9(第12世代以降)/Ryzen 7・9 7000番台以降
※用語補足:CPUはパソコンの中核となる処理装置で、映像のレンダリングやエフェクト処理の速度に大きく関係します。
ポイント:動画編集では複数のエフェクト処理やトランジション、レンダリングなどでマルチスレッド処理が要求されます。スレッド数が多いCPUほどこれらの作業を並列処理できるため、快適な編集が可能です。
GPU(グラフィックス)
- 軽作業:内蔵GPU(Intel Iris Xe、Ryzen Radeon Graphics)でも可能
- 重めの編集:外部GPU(RTX 4060相当以上)が理想
※用語補足:GPUは画像処理に特化したプロセッサ。編集ソフトのリアルタイムプレビューや書き出し時に重要です。
ポイント:DaVinci ResolveやPremiere ProではGPUアクセラレーションによりリアルタイムプレビューやエンコード処理が高速化されます。特にカラーグレーディングやノイズリダクション処理などはGPUへの依存度が高く、外部GPUを搭載したモデルでないとパフォーマンスが大きく落ちます。
メモリ(RAM)
最低:16GB 理想:32GB以上
※用語補足:RAMは一時的にデータを保存する場所で、同時に複数の作業を行う動画編集には容量が重要です。
ポイント:動画編集ソフトは多くの一時ファイルやキャッシュを扱います。特に4Kや複数クリップを同時に扱う編集では16GBでは足りず、スワップ発生で処理が遅延することがあります。32GBあれば安定して作業できます。
ストレージ
最低:500GB SSD(NVMe推奨) 理想:1TB以上 + 外付けSSDまたはHDD併用
※用語補足:SSDは従来のHDDよりも読み書きが速い記憶装置。NVMeはその中でも最も高速な規格です。
ポイント:動画素材は数分の素材でも数GBに達します。作業中に必要なキャッシュ領域も加味すると、500GBではすぐに足りなくなるため、1TB以上を推奨。また、読み書き速度の速いNVMe SSDが望ましいです。
実際におすすめのミニPC構成(2025年版)


以下は、2025年時点で動画編集に適したとされる最新のミニPCモデルです。用途や編集ソフトの負荷に応じて選べるよう、それぞれの構成と特徴を詳しく紹介します。
1. Minisforum UM790 Pro


- CPU:AMD Ryzen 9 7940HS
- GPU:Radeon 780M(内蔵)
- メモリ:32GB DDR5(最大64GB)
- ストレージ:1TB M.2 PCIe 4.0 SSD
- 特徴:フルHD〜軽めの4K編集まで幅広く対応可能。冷却性・静音性も優秀で、デザイン性と拡張性のバランスが取れたモデル。
2. Apple Mac mini M4 Pro


- CPU:Apple M4 Proチップ(最大14コアCPU/20コアGPU)
- メモリ:最大64GBユニファイドメモリ
- ストレージ:最大2TB SSD
- 特徴:Final Cut ProやAdobe Premiere Proで最適化されたパフォーマンス。Apple製ソフトとの親和性が高く、特にMacユーザーにおすすめ。
3. AtomMan G7 PT


- CPU:AMD Ryzen 9(上位モデル)
- GPU:Radeon RX 7600 XT(ディスクリートGPU)
- メモリ:32GB
- ストレージ:1TB SSD
- 特徴:eスポーツ対応のゲーミングスペックながら、動画編集でも安定したパフォーマンス。GPU処理が多い作業に向いている。
4. Beelink SER8


- CPU:AMD Ryzen 7 8845HS
- GPU:Radeon 780M(内蔵)
- メモリ:32GB
- ストレージ:1TB SSD
- 特徴:コストパフォーマンスが非常に高く、軽〜中程度の動画編集には十分対応。静音性や電力効率も優秀で、入門機としておすすめ。
これらのモデルは、処理性能だけでなく、冷却設計やポート構成、静音性、拡張性も含めて選定されています。動画編集用にミニPCを検討している方は、用途に応じてこれらのモデルを比較検討してみてください。
ミニPCで動画編集する際の注意点


排熱とファンノイズ
小型筐体では高負荷時に熱がこもりやすく、熱による性能低下(サーマルスロットリング)を引き起こす可能性があります。これにより処理速度が落ちたり、突然のシャットダウンにつながることもあるため、排熱設計の良いモデル選びと、通気性の良い設置環境の両方が重要です。
※用語補足:サーマルスロットリングとは、PCが熱を持ちすぎたときに故障を防ぐため、意図的に性能を落とす機能です。
拡張性の限界
ミニPCは省スペース設計のため、一般的に拡張スロットが限られています。メモリやストレージの増設可否、外部GPUボックス(eGPU)の接続可能性など、スペック表だけでは分からない部分に注意が必要です。eGPU対応機でもThunderboltのバージョンや帯域によって性能が制限されることがあります。
※用語補足:eGPUとは外付けGPUのことで、Thunderbolt経由で接続し、グラフィック性能を強化できます。
モニターや周辺機器との接続性
動画編集では色精度の高いモニターや2画面構成が望まれます。そのためHDMIやUSB-C(DisplayPort Alt Mode対応)、Thunderboltなどの出力端子が複数あるかも重要です。USBポートの数が足りない場合は、外付けHDD・カードリーダーとの接続が煩雑になることもあります。
まとめ
ミニPCで動画編集を行うことは、もはや特別なことではありません。近年のミニPCはCPU・GPUの進化により、従来のノートPCやデスクトップと比較しても遜色ない処理性能を持つモデルが増えています。
ただし、編集する動画の解像度や使用するソフト、作業の頻度によっては、必要なスペックや快適性に大きな差が出ます。そのため、「とりあえず使えそう」ではなく、「自分の編集スタイルに合った構成かどうか」を見極めることが重要です。
本記事で紹介したように、CPUの世代やスレッド数、GPUの有無、メモリ容量、SSDの規格と容量、そして放熱設計や端子の種類など、注意すべきポイントは多岐にわたります。ミニPCだからといって性能が劣るわけではなく、用途に合ったモデルを選べば十分にプロフェッショナルな動画編集も可能です。
軽い編集を気軽にこなしたい方には内蔵GPU搭載モデル、本格的に4K編集やエフェクト処理を行いたい方には外部GPU搭載モデルと、選択肢も広がっています。GEEKOMやMINISFORUMなど信頼性の高いブランド製品であれば、耐久性やサポート体制も安心材料のひとつです。
ぜひ、この記事を参考に「サイズも性能も妥協しない」ミニPC選びをしてみてください!